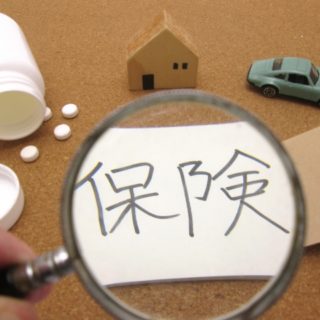ゴリFP
ゴリFP CFP試験の中でも金融資産運用設計は、苦手な人が多いと言われています。私は個人的には嫌いな課目ではなかったのですが、それでも苦手な問題はありました。どのように克服したのかなどを含めて解説したいと思います。
金融資産運用設計の頻出分野について

CFP試験のテキストをみると金融は厚く、範囲が広いことがわかります。
最近の問題を見ていると、概ね以下のような内容が出題がされています。
- GDP関連
- 展望リポートなどの内容
- 日本の金融政策、財政状況
- 海外の金融政策など
- 預金などの運用による収益(計算)
- 財形関係・確定拠出年金
- 株式・配当・公社債(計算)
- 割引債、利付債権(計算)
- デュレーション
- 投資信託の価額
- ポートフォリオ関連
- 為替関連(計算)
- オプション取引の戦略
- 最近の制度改正・時事的な問題
もちろん、これで全てという訳ではないです。
ただし、全ての範囲を網羅して勉強するのは、とても大変ですので、過去問から傾向を掴んで勉強していくのが合格への近道だと思います。
過去問を解いていけば、自然とその内容がわかってくると思いますが、ここではコツなども含めて私の勉強したことや解答のコツなどを説明したいと思います。
1. GDP関連
GDPは経済指標としてとても重要ですし、ニュースや新聞では頻繁に流れてきますので、ある程度のことは理解していると思います。
とはいっても、GDPの構成要素や三面等価(生産、支出、分配)、三面等価のそれぞれの中身など、ぱっと答えられる人は少ないと思います。
文字だけ見ても頭に入れるのは難しいので、YouTubeなどの動画でGDPを説明しているものがありますので、そういったものを見ながら勉強していくと記憶に残りやすいと思います。
2. 展望レポートなどの内容
市場において、日銀の金融政策はとても大きな関心ごとです。
日銀の金融政策決定会合の発表の日などは、株式や債権市場が大きく動くことがあり、為替などにも影響を与えるため、世界中から高い関心を集めています。
そういった政策について、背景や目標、現状の日本経済を説明しているものが、経済・物価情勢の展望(展望レポート)になります。
そのほかにも、日銀短観や金融システムレポートなどの内容は、そのまま穴埋めになったりして出題されます。
暗記する必要はありませんが、試験直前に過去に出題された部分を確認しておくと、正答率が高くなると思います。
中でも展望レポートは出題される傾向が高いので、以下のものが押さえておいた方がいいでしょう。
- 6月試験・・前年10月の展望レポート
- 11月試験・・同年4月の展望レポート
どちらも、「基本的見解」と「背景を含む全文」が公表されていますが、最低でも概要版である「基本的見解」を読んで理解しておきましょう。
展望レポートでは独特な言い回しや、聞きなれない言葉が出てきます。こういった言葉が試験問題の選択肢になっていることもあります。
日銀のレポート関係の問題は2問〜4問程度出題されることがありますので、しっかりと見ておくといいと思います。
3. 日本の金融政策、財政状況
展望レポートの内容とも通じますが、日銀の金融政策の内容は重要です。
- 現在の金融政策の内容
- 目標
- いつから行なっているか(時系列で把握)
- 今後の政策について
こういったことは把握しておくといいでしょう。
4. 海外の金融政策など
日本以外でも、中央銀行が様々な金融政策を行っています。
中でも、アメリカ、EUの動向は重要です。
日本の金融政策とは逆のことを行っていたりしますので、「どうせ日本と同じだろう」などと考えず、把握しておいてください。
5. 預金などの運用による収益(計算)
最初の計算問題になることが多いのが、預金が3年後にどれほどのリターンになるかなどを把握する問題です。
計算においては、単利か複利か、毎年税金を取られるのか取られないのか、といったことが重要となります。
毎年の税引後の金額を翌年に繰り越しながら、複利で計算していくという問題が多いです。
外貨預金を絡めた問題が出題されることもありますので、苦手な人は後回しにしていい問題だと思います。
6. 財形関係・確定拠出年金
財形は年金や住宅などの種類、途中解約や目的外利用の税制などがよく出題されています。
また、このところ増加しているのが、個人型確定拠出年金(iDeCo)です。
少し前に大きく制度が変わったのですが、その改正の施行日が少しずつ到来しています。
改正内容はCFP試験では頻繁に出題されますので、元の制度内容とともに、改正内容をしっかりと理解しましょう。
なお、iDeCoはいい制度ですので、自分でやってみるのもいいと思います。
タックスやリスク、ライフでも出題されることがありますので、しっかりと押さえておくことで、他の課目でも応用できます。
また、NISAや積立NISAの内容や違い、iDeCoとの違いについても押さえておきましょう。
7. 株式・配当・公社債(計算)
取得単価の計算や、税金の源泉徴収可否、確定申告すべき所得額などを計算する問題です。
源泉徴収される場合とされない場合などを把握しておけば、難しくない問題ですが、意外にも計算ミスをしやすい問題だと思います。
時系列に株式などの取得と源泉徴収の状況を確認しながらやれば、ミスのないように繰り返し練習しましょう。
8. 割引債、利付債権(計算)
問題集だと、いくつか公式を覚えるように説明しているものもありますが、個人的には一つの式を理解しておくことで、あとは変形などして解くことができました。
- P × (1+r)n = 100
P:価格 r:利回り n:年
これは割引債の式になりますが、複利計算の式と同じですので、覚えるまでもないという感じかもしれません。
それと、利付債の式も合わせて把握しておきましょう。利付債の式も基本的には上記の式の組み合わせになります。
これを元にすれば、いろいろと応用ができると思います。問題を解きながら理屈を理解すると、あとあと楽だと思います。
9. デュレーション
個人的にイメージしづらかったのがデュレーションです。
まず、デュレーションとは何か、デュレーションの数値の単位はなにか、といった理屈をどうにかして頭に入れました。
そして、まず式は丸暗記して、覚えてから式の理屈を理解していきました。
式も覚えてしまえば、なんてことはありません。
出題頻度が高いので、とにかく慣れてしまい得点源にしてしまいましょう。
10. 投資信託の価額
投資信託の価額の推移などから、基準価額や普通分配金、特別分配金を計算します。
簡単なようで、間違えやすい問題だと思います。私自身ミスが多かった問題です。
特に基準価額を求めるものはミスしやすいので、注意しながら問題を解くことが必要です。
11. ポートフォリオ関連
ポートフォリオに関する主なものは、標準偏差などから期待収益率を求めるものや、シャープレシオ、資本市場線、CAPMなど、範囲としてはいくつか項目があります。
標準偏差や期待収益率、シャープレシオについては、問題集などの解答から解き方を覚えてしまいます。
資本市場線、CAPMについては、グラフが出題されますので、グラフに表示されている縦軸、横軸、線などをすべて頭に入れてしまいます。
それぞれは単純な計算や内容だったりですので、理解しやすいと思います。
12. 為替関連(計算)
為替に関する問題は苦手は人が多いと言われていて、丸ごと捨てちゃう人もいると思います。
個人的にはあまり苦手意識はなかったのですが、やはり問題を理解して計算ミスせずに解答に行き着くのは簡単ではないです。
解答のコツとしては、「1ドル=110円で10000口買った」など、問題では一般的な事例に合わせていますが、問題は為替レートや損益分岐点など、口数に関係ない解答が求められるのが普通です。
「1口買った」ということにして、計算を進めていくと、余計な計算をせずにすみますので、計算ミスも少なくなっていいと思います。
また、気をつけたいのが、為替レートの中値と為替手数料(片道)です。
例えば以下のレートであれば・・
- 為替レート(中値)・・110円
- 為替手数料(片道)・・0.5円
為替の両替をする場合、
- 円→ドル ・・ 1ドル=110.5円
- ドル→円 ・・ 1ドル=109.5円
こういった問題の前提は、計算をしているうちに忘れてしまったりします。
十分に注意して、問題を解いていきましょう。
13. オプション取引の戦略
オプション取引については、しっかりと理屈を理解するのが大変です。
実際に取引したことのない人にとっては、なかなか頭に入らないと思います。
オプション取引には以下の4種類があり、組み合わせによって戦略があります。
- コールの買い
- コールの売り
- プットの買い
- プットの売り
とはいえ、ほぼ毎回出題されていますので、パターンとして覚えてしまうのがいいと思います。
オプション取引の利益と損失を表したグラフが必ず問題に出ます。グラフのパターンを覚えてしまえば、簡単に解答できるようになります。
14. 最近の制度改正・時事的な問題
CFP試験は全般的に制度改正に関する問題が多く出題される傾向にあります。
マイナンバー制度、株や配当に関する金融税制、所得税や住民税の問題、金融商品販売法、仮想通貨など、幅広く出題されています。
ニュースなどで気になったものは、少し深く調べて見たり、人が興味を持ちそうな情報を集めたりすることが必要かもしれません。
新しい制度については、国や地方自治体がパンフレットなどを作成して広報していますので、参考になると思います。
ちなみに、役所などで配布しているパンフレットは、問題集よりもわかりやすく、正確に制度を解説していますので、一度手に取ってみるといいでしょう。
金融の計算問題の注意点

計算問題を解くときに注意しなければならないのが、何を問われているかです。
したがって、以下の内容が書かれている箇所にマル印などを付けておきましょう。
- 税引後や税引前か
- 問題で指定されている利率の期間
- 四捨五入
中でも私がミスをしがちだったのが、利率の期間です。
問題で3ヶ月の利率が0.01%だった場合、年利としては4倍の0.04となるわけです。
解答は年利で解答することがほとんどですので、ここを確認していないと間違えてしまうわけです。
定番の問題は慣れるまでやろう!
過去問や問題集をやっていると毎年出題されている定番問題があるのがわかります。
他の課目でも同じなのですが、とにかく定番問題を落とさないようにします。
また、過去問に出てこないような問題は、勉強しても出題される可能性がわかりませんので、ある程度割り切ってもいいと思います。
過去問をやり尽くせば、ある程度の応用はできるようになっているはずですので、あまり恐れなくていいと思います。
試験の時間について
すんなりと解答をしていけば、時間をあまらせることも可能だと思いますが、計算問題でハマってしまうと、いくら時間があっても足りないことになってしまいます。
私も本番試験で計算問題にハマってしまい、結局ギリギリで試験終了となりました。
わからない問題は考えずに適当にマークするか、後回しにしましょう。
金融はCFP試験の中で最初の受験課目になると思いますので、時間配分で失敗することのないよう、注意してください。
これまでの試験の合格ライン
| 合格ライン(50問中) | |
|---|---|
| 2019年度11月 | 27問 |
| 2019年度6月 | 27問 |
| 2018年度11月 | 29問 |
| 2018年度6月 | 27問 |
| 2017年度11月 | 29問 |
| 2017年度6月 | 29問 |
| 2016年度11月 | 30問 |
| 2016年度6月 | 27問 |
※日本FP協会HPより
まとめ
金融資産運用設計の勉強法について、ポイントを説明してきました。
計算問題などの定番問題に慣れて、直前は日銀の資料をしっかりと読み込んでおけば、十分に合格点に達すると思います。